入院や手術が必要になったとき、
「医療費が払えなかったら…」と不安に思い、
若い時に民間の(〇〇生命)の医療保険(入院)に加入した。
いまでも、後悔しています。
入って安心ですが、支払に不安です。
『無駄に保険料を支払ってない?』と思う事もあり、
(以前にニュースや選挙でも話題になっていた)
「高額療養費制度」を調べてみました。
※最後に(比較的わかりやすい)高額療養費制度の
厚生労働省や協会けんぽの公式サイトのリンクを掲載してます。
詳細は各サイトでご確認ください。
個人的な結論:加入するなら都道府県民共済で充分
私も40代で、毎月の民間保険料の支払いは
キツイ!!
リタイア時には少ない年金でしょうから、
シンプルで、低額に抑えて、老後に備えたい。
結論:高額療養費制度+都道府県民共済(2000円)で十分と思う
持病がなければ、
民間保険も都道府県民共済2000円で十分よくない?
がんは2人に1人と聞きます。
がん保険は高いです。
がん保険支払(払う・減る)< 貯金(増える・備える)
高額な保険料を支払うより、コツコツ貯蓄することで
減るばかりの保険を支払うよりは
貯金するほうが賢いですよね。
保険も必要なら、
備える方が安心は安心です。
高額療養費制度ってなに?
高額療養費制度は、1か月の医療費が高くなったとき、
決められた上限額を超えた分が払い戻される仕組み です。
たとえば、100万円の手術を受けても、
実際の自己負担は おおよそ8万円程度(※年収にもよります) で済むことが多い。
自己負担の目安(70歳未満の場合)
- 年収約370~770万円:
→ 1か月の上限は 約8万円 - 住民税非課税の世帯:
→ 1か月の上限は 約3万5千円
つまり、医療費が何十万円、何百万円とかかっても、
自己負担はこの金額までに抑えられる仕組みです。
| 所得区分 | 自己負担限度額(1か月あたり) |
| 年収約1,160万円~ | 約252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 年収約770~1,160万円 | 約167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 年収約370~770万円 | 約80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| ~年収約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
参考)高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
参考)高額療養費簡易試算(70歳未満用) | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
でも、これが長期間、毎月支払が必要となる患者さんには
自己負担限度額が見直しされた場合、負担は大きくなりますし、
高齢社会になる一方なので財源はどうするの?というetc
以前ニュースで話題となっていました。
高額療養費の対象費と申請方法
対象となる費用は
- 健康保険が適用される入院・外来・手術・薬代
- 同一月、同一世帯での合算も可能
- 保険外診療(自由診療や差額ベッド代、食事代)は対象外
申請方法と流れ
① 支払後に申請して払い戻しを受ける場合
医療費を窓口で一旦支払→健康保険組合や協会けんぽ、市区町村に「高額療養費支給申請書」を提出→2~3か月後に払い戻しが口座に振り込まれる【払い戻しに時間がかかる。】
② 事前に限度額適用認定証を利用する場合
健康保険組合などに申請して「限度額適用認定証」を取得→病院の窓口に提出→支払時から自己負担額が限度額までに抑えられる
③マイナ保険証を利用する場合
医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法で医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法【これが一番負担が少なくて済む】※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください | 広報・イベント | 全国健康保険協会
じゃあ、民間の医療保険って必要?
ここまで読むと「じゃあ民間保険はいらないのでは?」と思いますよね。
確かに、高額療養費制度があるので
入院や手術にかかる基本的な医療費は、かなりカバーされます。
ただし、こんなケースでは民間保険が役立ちます:
- 入院中の 差額ベッド代(個室料) は高額療養費の対象外
- 交通費や付き添いのための生活費、仕事を休むことによる収入減は補償されない
- 長期入院や先進医療を受けたいときに備えたい
つまり、医療費そのものは公的制度で守られますが、
「医療以外の出費」や「より手厚い保障」を望むなら民間保険が安心
高額療養費+都道府民共済の組み合わせ例
都道府民共済の基本内容
都道府民共済は、東京都民が利用できる共済制度で、
シンプルで低コストなのが特徴です。
- 掛金:月2,000円または4,000円(コースによる)
- 入院保障:日額5,000円(総合保障型の場合)
- 手術保障:2.5~10万円(手術内容による)
※東京都民共済の一般的な総合保障2型(2,000円コース)の例です。
※高齢になると加入できません。
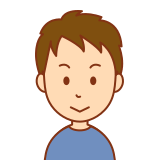
69歳まで加入可能、継続は85歳まで、
補償内容が変わります。
「その時は致し方ない。」と割り切っています。)
高額療養費+都道府民共済加入の場合、ざっくり見込
- 例:100万円の手術+7日間入院(年収500万円)
- 高額療養費を利用 → 自己負担は 約8万円
- 都道府民共済から給付 → 1日5,000円 × 7日 = 3万5千円
- 実質負担:8万円 − 3万5千円 = 約4万5千円
民間保険は必要?
高額療養費制度と都道府民共済があれば、
入院・手術による医療費の大部分はカバーできる。
ただし、こんな場合は追加で保険が役立ちます:
- 差額ベッド代(個室料)や食事代など、保険が効かない費用が心配
- 長期入院で仕事を休むことによる収入減に備えたい
- 先進医療を受けたい
まとめ&詳細リンク
- 高額療養費制度で医療費の上限はかなり低く抑えられる
- 都道府民共済(月2,000円)で入院5,000円/日+手術給付金も受け取れる
- 多くのケースでは「公的制度+共済」で十分
- さらに備えたい場合は、就業不能保険や先進医療特約など、目的を絞って選ぶのが◎
高額療養費制度の比較的わかりやすいサイト
| 項目 | 内容 |
| 制度の目的 | 医療費が家計に過重な負担とならないよう、自己負担に上限を設け、超過分を国が払い戻す仕組み (内閣府) |
| 自己負担限度額 | 年齢や所得によって異なる(所得区分ごとの具体的な額は厚労省・健保協会サイト参照) (協会けんぽ, ほけんの窓口) |
| 世帯合算 | 同一世帯内で複数人が同月に医療費を支払った場合、自己負担額を合算できる(70歳未満には条件あり) (協会けんぽ) |
| 多数回該当 | 同じ世帯・保険者で1年以内に3回以上該当すると、4回目以降の限度額がさらに軽減される仕組み (協会けんぽ, 協会けんぽ) |
| 手続き方法 | ・窓口で支払後に申請して払い戻しを受ける方法・事前に「限度額適用認定証」を取得して窓口負担を抑える方法 (協会けんぽ, 協会けんぽ) |
高額療養費も多少は、変わっていくでしょうけど、
過度に不安になり過ぎず、
(民間)保険貧乏にならないようにしようと思った
今日この頃です。
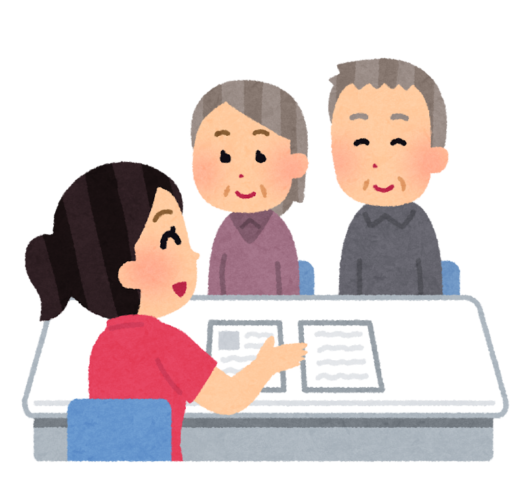
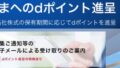

コメント